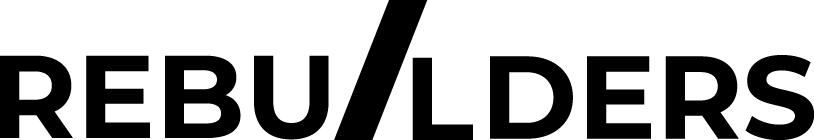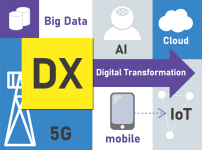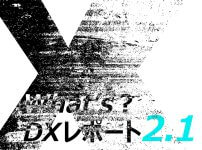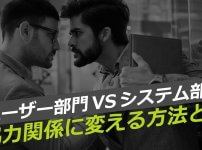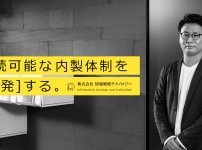新規サービス創出のカギはシステム内製
左からセブン銀行小林氏・斉藤氏・神野氏、情報戦略テクノロジー(IST)A.T氏・N.Y氏。 ご支援スタートから4年目に突入しており、14名の体制で参画中(2021年5月現在)。 お客様インタビュー第1弾として、「Myセブン銀行」アプリを内製で構築し2020年4月にリリースされた株式会社セブン銀行様にシステム内製のメリットや苦労をお伺いしました。またシステム内製にあたりご活用いただきました当社、情報戦略テクノロジー(以下IST)の「システム内製支援」についても語っていただきました。ISTからプロジェクトに参 ...
テレビ東京のオンデマンド事業を支えるパートナーシップ型の協業体制とは!
左からテレビ東京コミュニケーションズ三浦氏、望月氏、情報戦略テクノロジー(IST)KS氏、テレビ東京コミュニケーションズ岸氏。事業部門とシステム部門、そしてISTが三位一体となってオンデマンド事業を推進している。 今回インタビューにご協力いただきましたのは「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」などを運営しているテレビ東京コミュニケーションズ様です。自社サービスを成長させるためのお取り組みや、当社、情報戦略テクノロジー(以下IST)の「システム内製支援」について、プロジェクトマネージャーであるISTのK.S氏を ...
外部ベンダーの選び間違えを0にする、たった1つのポイント
DXレポートは不親切です。 「DXは、外部ベンダーとの共創が重要」と何度も書かれていますが、「どんなベンダーを選ぶのが適切か?」については一切書かれていません。ここが最も重要であるにもかかわらずです。 ベンダーを選び間違えると、DXは失敗します。 「仕様を固めてもらわないと開発できません」とエンジニアに突き返され、物事がスムーズに進まず、社内にハレーションが産まれ、DX自体頓挫する可能性も出てくるからです。 しかも、選び間違えてしまう可能性のほうがはるかに高い。 この悲惨な状況を回避していただくために、ベ ...
高齢者人口比率1位の秋田県が4ヵ年にわたるDX計画を打ち出す
本日ピックアップするDXニュースは、日本経済新聞が報じた「秋田県がDX推進 25年度まで4カ年計画」です。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC281SQ0Y2A320C2000000/(※外部サイト「日本経済新聞」が別ウィンドウで開きます。) 秋田県はデジタル技術を活用し、事業変革を進める2022~25年度のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進計画をまとめ、28日の県DX戦略本部会議で正式決定した。今後4カ年で県の行政手続きをすべてデジタル化し、情報関連産 ...
なるほど、だからアジャイル開発は失敗するのか
DX成功のカギをにぎる「アジャイル開発」。手探りで取り組みはじめている企業が増えていますが…うまくいかない、エンジニア側とケンカになってしまうという話、よく聞きます。 今日は、そんな症状に非常に効き目がよい本をご紹介します。 『エンジニアリング組織論への招待 著者:広井大地 出版社:技術評論社』 この本を読むと「アジャイル開発手法だけ取り入れてもダメ」で、まさに組織全体を作り変えなければいけないことがよく理解できます。 なぜダメなのか。それは、そもそもITエンジニアとビジネスマンはまったく違う生き物だから ...
DXレポート眠くなる方に朗報『対話に向けた検討ポイント集』
DX、理解したいけど、DXレポートはむずかしいしとにかく長い…特に、ITに明るいわけではない方にとってDXレポート読み込みはもはや試練です。(「DXレポート2」は56P、「DXレポート2.1」は24P。読み込みに1時間以上はかかります。) そんな方はまず、DXレポート2のダウンロードページ下にひっそり格納されている「対話に向けた検討ポイント集」という資料がオススメです。こちらの資料、ITにくわしくない方にもDXが理解できるように作られた紙芝居形式のファイルで、DXレポート2にも “経営層・事業部門・IT部 ...
「DXレポート2.1」10分で要点をつかむ!解説とオマケ考察
日本のDXを推進するため経済産業省から公表されているDXレポート。2018年9月に「DXレポート1」、2020年12月に「DXレポート2」、そして2021年8月に「DXレポート2.1」が公表されました。DXレポート2.1は、DXレポート2で触れられていた「ユーザー企業とベンダー企業の共創関係」について追加補足する内容で、DXを推進するにあたって特に重要かつ足かせになっている部分であることが強調されています。 本記事では、まずは要点を5分でつかめるよう内容をかみくだいてお伝えします。また、DXレポート2.1 ...
「DXとはなにか」を正しく理解できる、DXレポート2を解説。
結局、DXとはなんなのか。いろいろ情報を読み聞きしてきましたが、もっとも正確に、すべて網羅されているのが経済産業省発行の「DXレポート」です。まさに、DXの教科書。 しかし、2018年9月に公表された「DXレポート1(ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開)」では、カバーする範囲が広すぎるがゆえなのか企業側の正しい理解・実行につながらなかったことがのちに発覚。2020年10月時点の調査により「9割以上の企業がDXにまったく取り組めてない or ほぼ取り組めてない」ということが明らかになり ...
OBCと阿波銀コンサルティング株式会社がDX推進で協業開始
勘定奉行・奉行クラウドを始めとする業務システムを企画開発、販売運営する株式会社オービックビジネスコンサルタント(以下、OBC)は、阿波銀コンサルティング株式会社と協業し、阿波銀行グループのお客様を中心の対象とし、主に中小企業の経営課題の解決、業務効率化を、地域密着型で支援することを発表しました。 PR TIMESのプレスリリースを参照する場合はこちら(※別ウィンドウが開きます)> これにより、地域密着型でのデジタルトランスフォーメーション (以下、DX) の推進に取り組みたい意向です。 協業の背景 デジタ ...
ブロードリーフが「.cシリーズ」に、「スーパー検査員」の搭載を発表
【「スーパー検査員」について】 「スーパー検査員」は、自動車ディーラー、および指定整備工場において、車検業務に従事する「自動車検査員」の業務負荷の軽減やミス解消のためのソリューションです。車検・点検における工程管理を見える化できる「工程管理機能」や記録簿への記入漏れや入力ミスを防ぐための「入力チェック機能」などを搭載し、サービス部門の生産性向上とコンプライアンス強化を実現します。 このたび、「.cシリーズ」に搭載される「スーパー検査員」は、車検・点検に特化した機能に加え、電子記録簿保存への対応等、ユーザー ...
大日本印刷が京都市と連携し「京都館PLUS X」を開設することを発表
大日本印刷株式会社(本社:東京 代表取締役社長:北島義斉 資本金:1,144億円 以下:DNP)は、京都市と連携して、伝統工芸や観光資源等の京都の魅力を体験し、人と人が交流できるバーチャル空間「京都館PLUS X」を構築し、3月17日(木)にオープンします。「京都館PLUS X」は、DNPが2021年7月から運用中のバーチャル空間「渋谷区立宮下公園 Powered by PARALLEL SITE(パラレルサイト)*1」を活用して開設し、国内外のどこからでも、いつでも京都の魅力に触れ、体験して楽しむことが ...
システムよりも先に、チームを創れ。サービスの絶望的状況を救ったチームマネジメントとは
システム開発を内製化する企業が増える一方、さまざまなトラブルに見舞われプロジェクトが停滞してしまうケースが後を絶ちません。今回は、危機的状況が積み重なり続けていたサービスを復活させることに成功したエンジニアのエピソードをご紹介します。サービスを成長させ続けていくことのむずかしさ、一人のスーパーエンジニアではどうにもならないこと、チーム創りがいかに重要であるかがよく分かるお話です。 D.O氏プロフィール:新卒で入社したSES企業にてシステム運用と検収を6年以上経験する。システム運用の中で培われた視点を持ち味 ...
DX成功のカギを握る!!ユーザー部門とシステム部門の関係を構築する方法とは
ユーザー部門からの依頼が一方通行すぎて調整できず、プロジェクトを円滑に進められていない!と課題を感じるシステム部門。一方、システムリリースが間に合わず事業が計画通り進まない!と感じるユーザー部門。よくある対立関係を協力関係に変える方法について、プロジェクトマネージャーのエピソードを交えながらお話します。 K.K氏 プロフィール:新卒で250名規模の独立系システム開発会社に入社し、約10年間、一括請負案件の見積もりから保守まで幅広く経験。その後、事業の拡大を行うため、関西事業所の新規立ち上げを経験。営業から ...
経営方針に即反応できる、DXが加速するインフラチームの作り方
7割が失敗するDX。その根本要因と言われている「経営層と現場の思いのズレ」を解消するチームビルディングについて、情報戦略テクノロジーテックリードエンジニアがエピソードを交えお話いたします。 Y.K氏プロフィール:新卒で通信基盤構築などを手がけている会社へ入社。主にITインフラ構築を中心にソフトウェア開発やPMなど、マルチに経験を積む。その一方で、請負エンジニアの立ち位置では本当の意味で顧客の役に立てないと感じ、情報戦略テクノロジーに入社。入社後はHRサービスを提供するエンドユーザー企業に常駐し、インフラチ ...
内製開発の成否をにぎる盲点!!システム障害につながる芽をつぶす「PMO」とは
内製でシステムを開発していくということは、ビジネスの状況に応じ永続的に開発し続けていくということです。ですが、多くのシステムは、開発を重ねるたび「負の遺産」が増大し、ゆくゆく使えなくなってしまうという運命・状況に陥っています。そこで必要になってくるのが「PMO」という存在。「プロジェクトマネジメントを横断的に支援し、システム障害につながる芽を細かくつぶしていく存在」ですが、その重要性についてより具体的にご理解いただけるよう、弊社PMO 兼 リーダーエンジニアの取り組みを紹介します。 H.O氏プロフィール: ...
今話題のコンテナ技術!ビジネスメリットに繋がるコンテナの基本を解説!
デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が加速し、ソフトウェアやサービスの開発スピードがビジネス成功への大きな影響を与えており、どのように効率良くシステムを運用するかが重要となってきました。それらを実現するために、短期間で要件定義からリリースまでを反復させるアジャイル開発や、アプリケーションの開発、配備、管理に優れた運用することが求められます。こうした背景から、今回はそれを解決する新しい仮想化手法として「コンテナ」と呼ばれる技術を使用した際のビジネスメリットについて紹介致します。プロダクトオーナー、シ ...
リリース遅延・不具合多発を劇的に解消!!シン・テックリード流プロジェクトマネジメントとは!?
IT人材不足の深刻化により、プロダクトオーナー(PO)やスクラムマスター(SM)がプロジェクトマネージャー(PM)の兼務が通常化しています。ですが、それぞれ役割が大きく異なることにより実質PM不在の状態になってしまい、システムの不具合やリリース遅延が多発するというケースが増えています。そんな中、テックリードがプロジェクトマネジメントを兼務することで、プロジェクト状況を劇的に改善することに成功した事例をご紹介します。 T.O氏 プロフィール: 2012年 情報戦略テクノロジーに入社。WEBアプリ開発のリーダ ...
外部の優秀エンジニア頼り・不安定な体制を一変。「持続可能な内製体制」の開発方法、教えます。
内製化が進む一方、エンジニア採用がうまくいかない・そもそも雇用し続けること自体困難であることから、外部ベンダーとの「共創内製」が増えています。問題は、外部ベンダーの優秀なエンジニアが主力になってしまいがちなこと。優秀なエンジニアは引く手あまたであるため、いつか転職してしまいます。今回は、そんな不安定な状況をチームビルディングによって解消することに成功したエンジニアのお話をご紹介します。 Y.K氏プロフィール:法政大学経営学部を卒業後、200名規模の金融系SIer企業に就職。入社してからの2年、銀行の融資稟 ...
なんでも作れるわけじゃない!!ローコード開発に飛びつく前に知っておきたい3つのポイントとは?
昨今、システム内製化の手段として、プログラミングが出来なくてもアプリ開発などが可能なローコード・ノーコード開発が注目されています。しかし実情として、ローコード・ノーコード開発が一概にすべての内製開発にマッチするとは言えない現実があります。実際に、現場でローコード開発ツールを導入しているエンジニアに、注意点やメリットデメリットなど聞いてみました。 ローコード・ノーコード開発とはプログラミング言語を使用しない新しい開発手法 プログラム開発言語を使ったコーディングを全く、あるいはほとんどすること無くソフトウェア ...
【AWS/Azure/GCP】3大クラウドサービスをインフラエンジニア3人が点数付けてみた!
クラウドサービスの活用が急速に広まっている中で、クラウドサービスの提供者も様々な付加価値を付けシェア拡大を競っております。サービスが複雑化してくることでエンドユーザー企業にとって自社に最適なクラウド基盤を選択をすることが難しくなっているのではないでしょうか。また、これからクラウド移行を検討している担当者も同様かと思います。今回はクラウドの最前線で活躍するのエンジニアの対談を通じて各クラウドサービスのメリットデメリットを対談形式で分かりやすく紹介します。 株式会社情報戦略テクノロジー(インフラ部 基盤2G ...