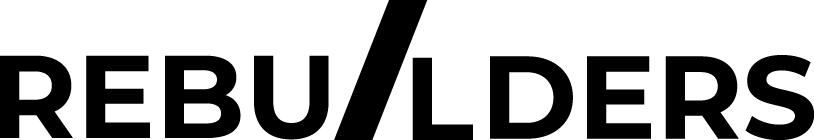情報発信元:https://www.t.u-tokyo.ac.jp/meta-school
(※外部サイト「東京大学工学部 」を別ウィンドウで開きます)
東京大学が今年新たに新設した学部である「メタバース(※)工学部」の設立記念式典が9月23日に開催された
(※)メタバースとは・・・仮想空間のことを指し、ユーザーは自分の分身としてアバターを使い仮想空間にアクセスします。メタバースの中では、アバターを使って会議をしたりゲームをしたりすることが多い。
開催場所はオフラインではなく、メタバース上で実施するという前例のないものだ。メタバース空間内の会場には安田講堂を再現したスペースが作られ、関係者たちのアバターはそこに集まり登壇社たちの話に耳を傾けた。
メタバース工学部で予定している活動は主に3つ。
1、学生&社会人向けに、AIなどを学ぶ機会の提供
2、中高生向けに、メタバースやデザインなどの工学の魅力を伝える事業の実施。
3、工学を修了した後の就職先情報の発信
東京大学はメタバース工学部による事業を通じて、自校の学生にとどまらず意欲のある人なら誰にでも学習機会を提供しく方針だ。事実、ソニーやリクルートなどの企業とすでに連携を始めており、社員研修などに東京大学の学習プログラムを提供していく予定だという
東京大学は今後、意欲ある人全てに学習機会を提供することで様々な人と共により良い未来を実現していきたいとコメントしている。
【執筆者コメント】
過去何度か当編集部でもメタバース工学部の設立については取り上げてきたが改めておさらいすると、本学部設立の目的としては「工学や情報に関する学びの機会をあらゆる人に提供する」を目的としている。その結論に至った背景としては、急速な社会の変化に対応できる人材、いわゆる「DX人材の不足」が背景にあり、東大としてはそれに歯止めをかけたいという思いがあってのことだ。
【参考記事】東大がメタバース工学部を設立、D&IとDX人材育成を推進
意欲さえあればあらゆる人を対象に東大の学習プログラムが受けられる環境作りをしていくと銘打っているが、実際にどんな学習プログラムになっているのか気になったので、以下整理してみた。(情報ソースは2022/09/29時点のメタバース工学部公式HPを参照した)
1、中高生向けプログラム
→工学の魅力を早い段階で理解してもらい、大学での学ぶことの意義や将来のキャリアについて伝えることを目的としたカリキュラム。オンラインを対面を組み合わせて実施。
カリキュラム一覧を見るに、起業を身近に感じてもらう授業や、アイディアの創出方法、モノ作りのプロたちの思考法を学べたりと、かなり魅力的なラインナップだ。これは中高生じゃない私も受けたいぐらいだと思っていたら、なんと応募自体は「誰も可」ということでビックリ。ただし定員はあるので抽選になる可能性は高そうだ。
2、社会人向けの学び直しを支援するプログラム
→AI、起業家教育、5Gなどの最新の工学に関する教育プログラムをオンラインで提供することを目的をしている。
こちらは一部のプログラムを除いて基本的には法人を対象としたカリキュラムとなっている。中高生向けプログラムとは少し毛色が変わり、データの解析・分析スキルを身に付けるものであったり、Pythonを身に付けるプログラミング講座、将来の起業家向けの講義であったりと、かなり実践よりの印象を受ける。こちらは残念ながら法人単位での申込となるので、残念ながら個人が気軽に参加はできない。
以上、2つのプログラムが10月よりスタートする。特に1については費用も無料で一般公募のプログラムとなっているので、かなりの大盤振舞いだと感じる。興味がある人はぜひ応募してみてほしい。
前回インテルが自治体にナレッジを提供するというニュースを取り上げたが、今回は大学が自校の持つ教育プログラムを提供していくというものであるが、何よりポイントとなるのは受講生側には年齢や立場、住んでいる場所などの制限がないことであり、より多くの人が工学・情報分野を身近に感じることができるようなカリキュラムが多いことだ。
【参考記事】「三豊市がインテルと協定、市のデジタル人材育成を加速する狙い」
さらに工学をより深く学んでいこうという人たちの入り口となるであろう本教育プログラムを、オンラインを活用して実施するというのは、東大にとって新しい取り組みとなり、東大としても自校の教育プログラムが多くの人に対して有用であるという実績を作ることができる。
いずれ受講生の中から有能なDX人材が生まれるという期待は大きく、ひいてはIT後進国と言われてしまっている日本を押し上げる人材が1人でも多く増えることを期待している。
執筆者/
リビルダーズ編集部 木城 秀人