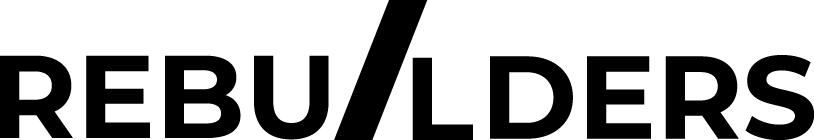DXという言葉が、DX推進の一番のガンになっている。
…かもしれない、というお話です。
DXを文字通り解釈すると「デジタルによってトランスフォーム (改革)すること」ですが、デジタル化を進めることでおのずと改革が進むようなイメージになる言葉です。
これはまったくの誤解であり、このこともデジタル化で終わってしまいがちな一つの要因になっている可能性があります。
今回はあらためて、誤解されがちなDXのXについてお話しします。
デジタル化とDXはこんなにもちがう
まず、あらためてデジタル化とDXのちがいについてお話しします。
デジタル化は2種類あって「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」に分かれます。その後、DXに到達するというのが一般的に言われていることです。
ですが、厳密に言うとデジタル化とDXは、まったく別物です。
デジタイゼーションとは…
アナログからデジタルへの変換
デジタライゼーションとは…
デジタル変換されたことで得られたデータを活用し、ビジネスモデルを再変換
DXとは…
デジタル化に伴い、企業組織を変革すること
DXという言葉が焦点を当てているのは、企業組織の変革です。デジタル技術を活用したビジネスモデルに適応する組織変革をDXと呼んでおり、デジタル変革がいくら進んでも、組織が変わらなければDXは成り立たないということです。
デジタルビジネスになると、これまでのビジネス基準では対応できないことがたくさん出てきます。
デジタルビジネスにはUX(ユーザー体験) を企画する人、改善する人など、従来のビジネスの枠組みでいう「間接部門」の人間が多く必要となり、彼らが売上に直結する働きを見せるようになるため、その評価をどうするべきかといったことも出てきます。
また最近トレンドのOMO。ユーザーにオンラインとオフラインを感じさせないマーケティング手法のことですが、オンライン(ECなど)で注文され、オフライン(お店)で受け渡したものは、オンライン事業部の売上なのか、オフライン事業部の売上なのか線切りがむずかしくなります。こうした次々と生まれては消えていくトレンドに対応していくことができる柔軟な組織体制も必要です。
あとで詳しくお話ししますが、UXの高速改善を基礎とするデジタルビジネスは命令型の組織体制では対応できなくなります。現場の判断でどんどん回していける体制に再構築する必要も出てきます。
デジタル化までは情シス・特設DX推進部隊でも出来ますが、DXは経営者じゃなければ出来ないというのは、組織体制・制度をぐるっと変革する必要があるためです。
命令型組織の撤廃
組織変革の中でも最も重要なのが、命令型組織の撤廃です。
これまでのビジネスは「売り切りモデル」でした。企業が良いと思うモノやサービスを開発し、大量に告知して売り切っていく”企業側に主導権がある一方通行”なビジネスです。
DXが目指すこれからのビジネスは、”ユーザー側に主導権がある双方向” ビジネスです。そのため、ユーザーと直接接点を持つ現場の考えを基準に柔軟に戦術・戦略を変革していく体制を築く必要があります。
これまでのビジネスと同様、上層部が指示する方向性通りに現場が動くロボット体制では、DXビジネスには適合しない ”レガシーな企業” になり下がっていきます。
「このアイディアは、自社のミッションに合致しているからすぐトライしてみよう」
「ユーザーのこのニーズは重要だから、すぐに自社戦略に反映させよう」
と現場メンバー一人一人が自律的に考え、フレキシブルに動く”対話型組織” への変革が必要です。
組織変革で変わったネットフリックス
もともとDVD郵送によるレンタル事業会社だったネットフリックスが、ストリーミング配信に切り替え一気に成長していったことはご存じかと思います。
ですが実は、この切り替えのタイミングで大きな危機に直面しています。
もともとネットフリックスは、DVD郵送レンタルとストリーミング配信をセットで月額10ドルで提供していました。その後、ストリーミング配信にフォーカスするために、DVD郵送とストリーミング配信を別会社に。DVD郵送月額8ドル・ストリーミング配信月額8ドル、セットで月額16ドルでの提供に踏み切りました。(つまり、DVD郵送だけをキャンセルする人が増える想定で)
すると、あっという間に80万人以上のユーザーが離れていき、株価が半分に下落。
ネットフリックス CEO リード・ヘイティングスは、周囲の意見を聞かず、独断で物事を進めてしまったことを悔い、そこから組織文化を180度変革します。
①自由な意見を育てる
アイディアがある人はメモを作成し、数十人の社員に共有。-10~+10の範囲で点数を付けてもらい、賛成意見と反対意見を集め、フラットに協議し、意思決定に反映させる仕組みにしました。
②一社員の反対意見も、まずテストしてみる
動画のダウンロード機能は不要ではないかという経営判断に、一人の社員が反対しました。その社員はドイツ・インド・アメリカでアンケート調査をし、結果20~70%の人がダウンロード機能を利用していることが判明。ダウンロード機能の導入を決定しました。
③すべての社員に裁量権を持たせる
一般社員にも決済権を持たせ、自身の判断で契約書にサインができるようにし、自分の意志でプロジェクトを動かせるようにしました。
④上司と意見が合わなくても実行させる
上司と意見が合わないアイディアも実行し、成功したら、上司は全社に向け「反対したが無事プロジェクトは成功した。私が間違えていた。」とアナウンス。失敗しても減点せず、なぜ失敗したのか本人に分析メモを作らせ、公開させるというルールを作りました。
つまりネットフリックスがやった組織改革とは、社員を奴隷化してしまう旧来の組織体制からの脱却。こうして現場の視点をフル活用したことが、DXの代表事例であるいまのネットフリックスを創りあげたということです。
対話型組織に変革する方法
命令型組織から、対話型組織への変革は一朝一夕で成し遂げられるものではありません。現場社員に至るまで経営目線で物事を考え、日々の業務にどう対応していくか自由に考えていく組織を創っていくということだからです。
まずは、経営層と現場の距離を縮めること。そのための施策があります。
①Google TGIF
Googleは、経営層と現場の距離が遠すぎることに強い課題意識を抱き、経営層が社員と話をする全社ミーティングを毎週金曜日に開催。これをTGIFと呼んでいます。TGIFは「Thank God It's Friday」の略で、もともとは無事一週間を乗り越え金曜日を迎えたことを神様に感謝する表現だそうです。
Googleほどの企業でも、現場の状況が上層部の目に触れにくくなってしまうことに対する課題意識をもっており、TGIFの目的はCEOと現場の距離を縮めることにあります。またその場で、社員からCEOに質問することができ、CEOからのフィードバックに対しサイト上で社員のコメントが集まるような工夫もなされています。
②トヨタイムズ
トヨタがいま、どんな未来を創ろうとしているのかをわかりやすく世の中に伝えるために創られた、CMとネットを融合させたオウンドメディアです。オウンドメディアというと、ブログ記事をたくさん掲載したメディアが一般的なイメージですが、CMと連動させてしまう作りこみはさすがトヨタです。
オウンドメディアというのは外部発信を意識したメディアですが、CMで大々的に世の中に公開することで、トヨタ社員も「あれだけ強く発信してる情報を社員が知らないわけにはいかない」という状況を作っているという裏目的があります。
こうした取り組みが重要なのは、ミッションワードだけで経営層の考えをわかってもらうのはむずかしいため。なぜそのようなミッションになったのか、そもそもどういう意味なのかなどその文脈・背景を伝えなければ考えは浸透せず、対話型組織がはじまりません。
従来の組織は「上層部の考えのすべてを現場が理解することは不可能。見ている視界がちがう。だまって信じてついてきてくれ。」になってしまいがちです。まずはこの状況から崩していくことが重要であり、高いハードルです。
GoogleはTGIFを通して、CEOと現場の距離を縮めることで、上司を飛び越えCEOに直接進言してしまうことが増えることも咎めないそうです。ただしその意見には上司をCCで入れることで誠実な関係性をつくることを前提としています。
まとめ「DXは、Xが8割」
DXはX、組織変革が重要というお話でした。
●DXは「組織変革」であり、デジタル化とは別物。
●評価制度や体制など大きな変更が必要になるが、命令型組織から対話型組織への変革が大きなテーマ。
●経営層と現場の距離を縮めることからはじめる。上司を挟んだ伝言ゲームをどれだけなくしていけるかがポイント。
ネットフリックスは例外的な話で、アメリカは働き手の流動性が高いこともあり、トップが変わるとミドルも一気に変わることが一般的です。そのため、比較的組織変革しやすい傾向がありますが、日本はそうではありません。
ここまでお伝えしてきた通り、デジタル化を進めたところで組織が変わらなければDXとは言えません。つまり、日本は特に組織変革に力を入れなければいけない国だということです。
デジタルによるトランスフォーメーションはどうしてもデジタルに視線が集中してしまいがちですが、デジタルではない変革にこそ力を入れるべき。いかにデジタル人材を集めても、UXを企画し推進していく非デジタル人材が不足していてはDXは進まないのと同じです。
参考:
アフターデジタル2 UXと自由 発行:日経BP社 著者:藤井保文
いまこそ知りたいDX戦略 発行:ディスカヴァー・トゥエンティワン 著者:石角友愛
執筆者
リビルダーズ編集部